
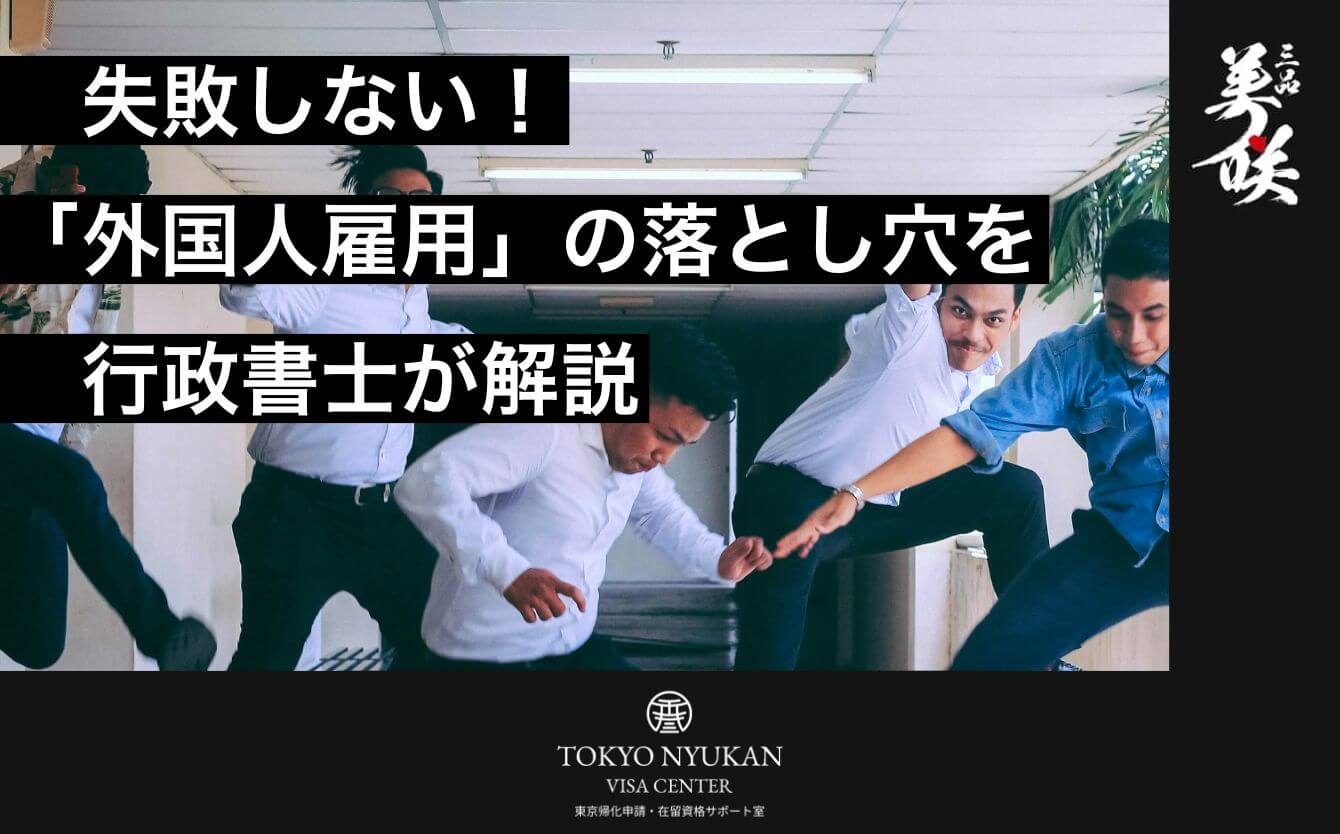




行政書士三品美咲事務所

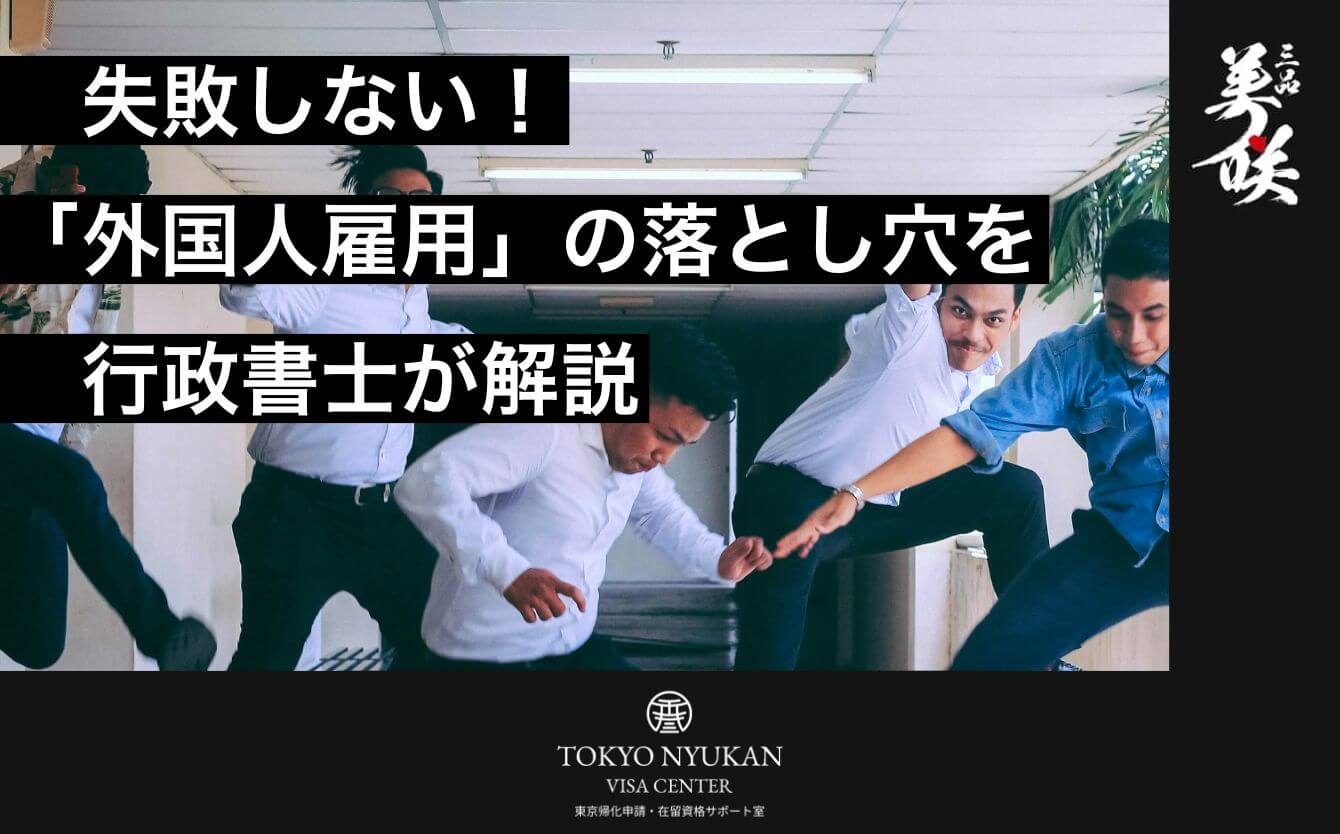
お世話になっております。三品美咲です。
私のホームページ「東京帰化申請・在留資格サポート室」へようこそ。
近年、人手不足を解消するために外国人雇用を検討する企業が増えています。しかし、外国人雇用には、特有のルールや注意点があり、それを知らずに進めてしまうと、思わぬトラブルに発展する可能性もあります。
今回は、外国人雇用で失敗しないためのポイントを、行政書士の視点から、わかりやすく解説していきます。

外国人雇用で気を付けるべきはズバリ「在留資格」「労働条件」「言語力」。ここを理解していないと、事業主が知らぬ間に不法就労に加担してしまう、あるいはせっかく雇ったのに職場でトラブルになった、という可能性が出てきます。
就労ビザを取得せずに外国人を雇用してしまった場合、不法就労となり、企業側も罰金や懲役刑などの重い罰則を受ける可能性があります。これについては次の章で詳しく解説します。
雇用において人種差別は絶対NG。日本人従業員より低い賃金で外国人労働者を雇用したり、外国人労働者に長時間労働をさせることはできません。すべて労働基準法に違反しますし、何より会社の信用問題になる可能性があります。
文化や言語の違いから、外国人労働者とのコミュニケーション不足が生じ、業務に支障をきたすこともあるでしょう。雇用する職場や内容によって、日本語検定などのスキルを見たり、通訳を用意したりする必要があるかもしれません。すでに在籍している日本人スタッフや、経営陣も異文化や外国語にある程度の寛容さが必要です。
外国人の雇用について「複雑だ」「面倒くさそう」と感じる方も多いかもしれません。ただし、在留資格において「永住権」を持っているか、永住権、もしくは日本人の家族。そして「定住者」という資格であれば、日本人を雇用するのとさほど大きな違いはありません。(細かい資格の内容はまた別の機会に解説しますね!)
一方で「技能実習」と「特定技能(1号・2号)」は一定の理解が必要です。これらは雇用形態や雇える業種に制限がかかります。こうした資格がないと、不法就労として罰則の対象になる可能性もあるため、ぜひ覚えておきましょう。
技能実習制度は、開発途上国への技術移転を目的とし、外国人に日本の技能を学び、母国で活かしてもらうことを目指しています。対象は77の職種で、最長5年の在留が認められています。企業は、技能実習生に対して技能指導や生活指導を行う義務があります。

一方、特定技能制度は、日本の深刻な人手不足を解消することを目的としています。16の産業分野において、一定の専門性・技能を持つ外国人材を受け入れ、即戦力として活用することが期待され、2019年に法律が制定されました。特定技能1号は最長5年、2号は無期限の在留が可能です。2号では家族の帯同も認められています。
行政書士は、外国人雇用に関する様々な手続きをサポートすることができます。
外国人雇用は、人手不足解消の有効な手段となります。しかし、適切な手続きや対応を怠ると、企業にとって大きなリスクとなる可能性も秘めています。
「外国人雇用を始めたいけど、何から準備すればいいのかわからない…」
「外国人雇用に関する法律や手続きが複雑で困っている…」
そんな時は、ぜひお気軽に行政書士にご相談ください。専門的な知識と経験を活かし、企業の皆様の外国人雇用をサポートさせていただきます。
行政書士三品美咲事務所では、外国人雇用に関するご相談を承っております。実際の経験をもとに、丁寧にサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。

